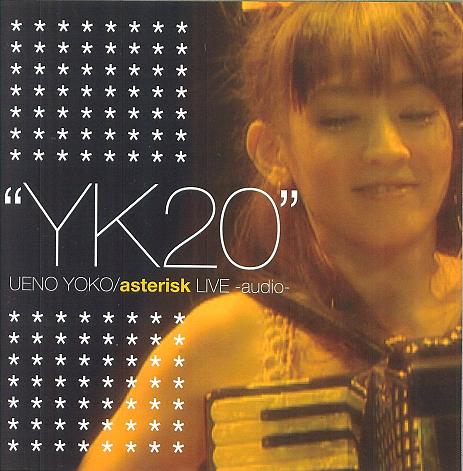落合徹也/粗品(1995年)
G-CREFのヴァイオリンニストによるソロアルバム。G-CREFの音楽性から、クラッシクをベースにした、多少偏屈なポップミュージックを予想するのだが、実際の音はバンド編成によるジャズロックである。特に女性スキャットボーカルが参加しているあたりのセンスは、70年代のヨーロッパのジャズロック、マイケルウルバニアクやZAOの音楽性を彷彿させる。 バッキングメンバーもドラムの村石雅行をはじめテクニック派がそろっており充実した演奏を聴かせてくれるが、音自体は演出がなく、かといってライブでの臨場感も欠け、物足りなさを感じさせる。その淡泊さが解消されればより魅力的になったと思われるだけに残念である。
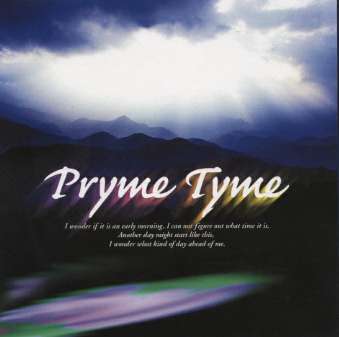
Pryme Tyme/Pryme Tyme(2000年)
元G-Crefの落合徹也参加のフュージョンバンドのデビュー作。編成はg、b、kb、drにe-vlの5人。フュージョン界の強者が集っているだけあってテクニックは抜群。極めてハードなプログレッシブフュージョンというべき内容に仕上がっている。ヴァイオリンはすべてエレクトリック使用、ハードな楽曲の中で、粘り気のあるプレイでギターとともにリードを取っているが曲によっては透明感のある音色で叙情的な部分をになっていて心地よい。全体的にヘビーな感じが強いが7曲目は優美さとかっこよさをともに持っている名曲。ヴァイオリン入りフュージョンとしては極めて完成度の高いアルバムに仕上がっている。
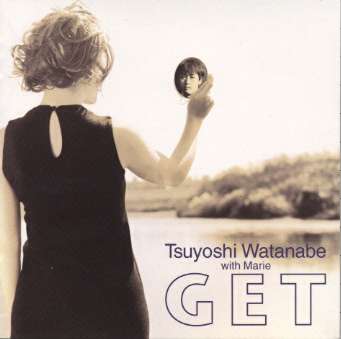
渡辺剛withマリー/GET(1996年)
落合徹也とともにG-CREFのヴァイオリンをつとめた渡辺剛のソロアルバム。クレジットからも判るように10曲中3曲はマリーという女性ボーカリストをフュチャーしている。その音楽性は落合徹也とは対照的に極めてポップで、このアルバムも綿密なプロデュースに基づいたアルバムとなっている。楽曲自体は、前記の女性ボーカルナンバー、ラップ、ロック、それにウェザーリポートのカバーと多彩だが、どれもBGMとして聴けるほどにコントロールされている。シリアスさという意味では多少物足りないが、しゃれたドライブのBGMとして十分通用しながらもバイオリンの魅力を味わえるなかなかな好作品となっている。「サラリーマン専科」のメインテーマも収録。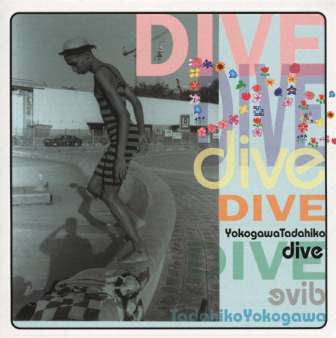
横川タダヒコ/DIVE(1995年)
アフターディナー、P-model、メトロファルスと日本のコアなバンドを渡り歩く異色の音楽家、横川タダヒコのソロアルバム。彼はヴァイオリンの他ギターやキーボードも扱いかつボーカルもとれるマルチな人で、このアルバムもそう言った様々な楽器と渋いゲストによるボーカルメインの作品である。そのひょうひょうとしてとらえどころのないキャラクターどおり、無国籍で不思議なポップスが展開される。バイオリンは3曲で弾かれる程度。その音は彼の楽曲同様アジア、中東の民族音楽の影響が微妙に感じられる。ソロというには短い、フレーズを次々と繰り出すことにより楽曲に幻惑的な雰囲気を醸し出している。
東京ホット倶楽部バンド/TRAIN BLUE(2000年)
ギター3人にベース、ヴァイオリンという5人編成でウェスタンスイング系のジャズミュージックを演奏するバンドの最新作。アコースティックギターのアンサンブルをメインとしたその音楽性は、アメリカ直輸入の乾いた叙情性を感じさせるもの。ヴァイオリンの大屋氏のオリジナル楽曲はStephan Grapperiを思わせる優美なSWING JAZZ。しかしそう言ったSwing的なナンバー以外にもCharlie ParkerやChick Corea、Jaco Pastoriusなど多彩なジャズも取り上げているが、どれも彼ら流にアコースティックにアレンジされ違和感がない。日本ジャズバイオリンニストの草分けである大矢氏は元々Bluegrassからスタートしたとのことだが、ここで聴かれる音はStephan Grapperi直系の滑らかにSwingするうつくしいものである。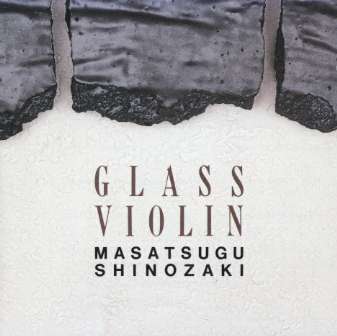
篠崎正嗣/GLASS VIOLIN(1988年)
70年代よりセッションミュージシャンやCM・映画音楽などのコンポーザーとして活躍するヴァイオリンニストの3枚目のソロアルバム。曲ごとにSAXや尺八などがゲスト参加するものの基本編成はヴァイオリン、キーボード、パーカッションというシンプルなもので、その編成でタイトルどおりの透明感のある美しいインスト作品に仕上げている。とはいうものの1曲目でのパーカッションの入り方や、4曲目でのエレクトリックヴァイオリン多重録音によるシンフォニー、7曲目のころころと表情の変わる曲展開など一筋縄では行かないアレンジや技量が見られ、聴くごとに発見のあるアルバムとなっている。ちなみに楽器はエレクトリックヴァイオリンをメインとしながら二胡やアコースティックバイオリンも使用している。
玉木宏樹・篠崎正嗣・中西俊博/LE MISTRAL-VIOLIN SUPER SUMMIT(1989年)
こんなアルバムが出ていたとは、と驚かされる巨匠3人によるコラボレートアルバム。それぞれ独創的な人たちだけに大いに期待するところだが このアルバムで聴かれるのはクラシックのアレンジやGrappelliのアルバムに入っているようなスイングジャズタイプの楽曲で、 おしゃれで上品だが、残念ながら新鮮な驚きはない。クラシックが判る人には、クラシック曲のジャズ的アレンジなどに魅力を 感じるのかもしれないが、あくまでクラシックの範疇の中でのこと。3人でアドリブをとりあったりする訳ではないので、 正直共演の魅力はあまり感じない。個人的にはラストの中西俊博とピアノの難波弘之のDuoによる即興曲の美しさが印象的だったが。

都留教博/月を作った男(1989年)
環境音楽、ヒーリングミュージックの領域で活躍する都留教博のデビューアルバム。現在では作曲家、アレンジャーとしての立場での仕事が多く、あまりヴァイオリンを全面にひくことのない彼だが、このファーストアルバムでは全編クラシカルで哀愁の漂うヴァイオリンプレイをきくことができる。楽曲は癖のないイージーリスニングでメロディアス、打ち込みリズムにアコースティックギター、シンセサイザーというバックにのって全編詩情豊かな泣きのメロディがヴァイオリンによって奏でられる。ただ楽曲の起伏がいまいちとぼしく、全体的に淡白なのが物足りないといえば物足りない。
都留教博+中村由利子/GEMINI(1998年)
ドキュメンタリーや環境ビデオなどの音楽を制作する作曲家でありヴァイオリンニストでもある都留教博とイージーリスニング系ピアニスト中村由利子のコラボレイトアルバム。このアルバムは元々北欧の世界を撮影した環境ビデオの音楽として制作されたもので、曲によってギター、キーボードなどのゲストが入りながら、1曲目の暖かいアップテンポナンバー以外は、きわめてやさしく切ない音楽が続く。元がBGMという性格上、個々の個性を主張するよりは、楽曲本意の編曲がされている。どちらかというと中村のピアノがメインに立ち、都留のバイオリンは曲の構成にあわせるよう控えめに演奏されている。同組み合わせであと2枚の作品が作られている。
川井郁子/The Red Violin(2000年)
芸大出身で、元々ソリストとしてクラシック畑で活躍していた彼女だが、よりコンテンポラリーな領域に活動の域を広げて発表したのが このアルバム。スパニッシュな要素を強く漂わせるアレンジによるクラシック曲と彼女のオリジナルが並ぶ。クラシック曲は、 アランフェス協奏曲やクライスラーの楽曲など元々哀愁味あふれる楽曲が選曲されており、それがよりジプシー風なアレンジを施されて 情熱的に演奏される。彼女自身の楽曲はゆっくりした曲調のものが多いが、やはり哀愁ただようものが多く、アレンジ曲との間に違和感はない。ちなみにバイオリンの音色は、アドリブやエレクトリックの使用はない完全にクラシックフィールドのものだ。
川井郁子/Violin Muse(2001年)
彼女のソロ2作目は前作同様、クラシックのアレンジ作品と彼女のスパニッシュ風オリジナル作品によって構成されている。取り上げられているクラシック曲は、バッハのシャコンヌ、ビバルディの夏、アルルの女、パガニオーニの奇想曲などヴァイオリンの曲としてはどれもおなじみのものばかりだが、今回は彼女自身のアレンジによって、前作以上に原曲とは異なるダイナミックな色づけがなされている。オリジナルは前作同様のスパニッシュ感覚あふれる叙情的なバラードたちだがこれも前作に比べてより完成度を増している。ということで全体的な印象はいいが、もうそろそろ違う展開も欲しいような気もする。

大津純子・佐藤允彦/PLATEAU SONG(1998年)
クラッシックのバイオリンニストとジャズから出発した現代作曲家によるコラボレートアルバム。すべてヴァイオリンとピアノによるDUOによって演奏される楽曲は奄美民謡やトルコ民謡などを素材としながら、極めて近現代音楽的和声によるアレンジがなされており、一聴した所では民謡であることに気づかないほどにモダンだ。どこかオリエンタルでありながら上品で優しく流れるこの音楽での大津のバイオリンはクラシックによるものだが的確な表現力でこのアルバムを完成させている。同コンセプトのアルバムがもう一枚出ている。
Chocolate Fashion/レア・チョコレート(1998年)
チョコレートファッションは、当初ヴァイオリンとチェロのDuoだったが、チェリスト脱退後はヴァイオリンニスト高島ちさ子の ソロプロジェクト名となった。その音楽はいわゆるクラシックや映画音楽、ポップスなどをヴァイオリンで演奏するものだが、 ロック的なダイナミックなアレンジ、分厚いバッキングもあって原曲とは違った魅力を醸している。バイオリン自体はクラシックベースだ が、エレクトリック楽器による分厚いアレンジによりクラシック臭は希薄だ。このアルバムはベスト&レアということでオリジナルはないものの多彩な楽曲を楽しむ事ができる。1曲目のダッタン人の踊りからしてクラッシクとは思えないおしゃれで切ないナンバーに生まれ変わっている。良質のヴァイオリンポップアルバムだ。
Chocolate Fashion/悪魔のロマンス(1996年)
チョコレートファッションが高島ちさ子のソロプロジェクトになってからの2作目。今回のアルバムはラテン的な音がテーマになっているようだが、アルゼンチンタンゴからチックコリアの「SPAIN」、SANTANAの「哀愁のヨーロッパ」からペレスプラードのマンボメドレーまで多彩な楽曲が並んでいる。しかし多彩ながらも哀感の漂うヴァイオリン向きの楽曲が多いということもありマンボ以外並べても違和感がない。ただこのプロジェクトにしてはポップな楽曲が少ないためか、アレンジに意外性が少なくダイナミックさに欠ける感がするのが少々残念。決して悪いわけではないのです。贅沢な注文。マンボにしてももう少し派手に壊れて欲しいところか。

向島ゆり子/RIGHT HERE!(1996年)
新宿Pitt inを中心に活動するヴァイオリン兼アコーディオン奏者のソロアルバム。個人的に、タンゴバイオリニストのソロアルバムという先入観を持ってこのアルバムを聴いたのだが、実際には、彼女の人脈であるジャズ系ミュージシャンが多数参加し、タンゴにとらわれぬ様々なラテン音楽の要素、そしてジャズやフリーといった要素を取り入れた、幅広い音楽性を持ったアルバムとなっている。特に2曲目のサンバや6曲目のインプロビゼーション、7曲目でのひえつき節のタンゴ化といった実験的な側面、それに3曲目の泣きの叙情性、ラスト曲での暖かいメロディに見られる歌心のバランス感覚が嬉しい。彼女のバイオリンは特に特徴のあるものではないが、そのコンポーサー、アーティストとしてのあり方は評価できる。
OU/OU(1988・94・95録音、2003年発表)
HANIWA、AREPOSなどでも知られるキーボードプレイヤー清水一登をリーダーとする変拍子ジャズロックバンドの初アルバムは88年と94、95年のライブ録音を発掘したもの。ヴァイオリンの向島ゆり子を始め渡辺等、今堀恒雄、矢口博康、松本治、近藤達郎、故篠田昌巳とその筋の凄腕をそろえたその音は変拍子づくしのあやしげな楽曲できめを入れまくるあやかしのチンドン屋という感じのもの。めまいのするようなゆったりした変拍子の上でヴァイオリンやサックスが郷愁を誘うようなソロを取る様は不思議なトリップ感をかもし出す。この不思議感のうちヴァイオリンの不安定感によってもたらされている部分は大きくこの大編成の中でも確かな存在感がある。とにかく凄いクオリティであるのは確かだが聴く人を選ぶのも確か。でもちょっと癖になる音だ。勿論好きな人にはたまらないだろうが。それにしてもこれでライブ録音というのはやはり凄い。

増田太郎/悩める息子(1999年)
この人を知ったのは、サンテレビの深夜音楽番組でチキンジョージでのライブ放送をしていたためである。彼はバックはキーボードだけという編成で、バイオリンを引きながら歌っていた。バイオリン兼ボーカルというアーティストは結構いるが本当に弾きながら歌っている人を見たのは初めてで「へえこんな人も居るんだ」と印象に残った。曲自体はニューミュージック調のポップスであったが、気になったのでCDを探して買ってみたのだが、残念なことにCDではヴァイオリンは曲の間奏に弾く程度で、ほとんどフューチャーしていなかった。曲自体は地味ではあるが味わいはあっていいのだが。
武川雅寛/とにかくここがパラダイス(1982年)
moon ridersのヴァイオリンニストによるソロアルバム。バックはmoon ridersのメンバー。楽曲はベンチャーズをはじめとするオールディースのカバーが中心で、全体的にリラックスしたムードがただようBGM風なものだ。ヴァイオリンは適度なテクニックによる安定したプレイだが、あまり派手に弾きまくることもない。かといってコンポーサーとして活躍しているかというと、本人のオリジナルは1曲のみ。というわけでヴァイオリンニストのソロとして聴くと、ん?ということになる。それよりはこのアルバムはmoon ridersのメンバーによるリラックスしたセッションアルバムととらえた方がいいのだと思われるのである。上野洋子/YK20〜20周年につき初ソロ(2007年)
トラッドの要素を取り入れた叙情的なポップスで人気を博したユニットZabadakに95年まで参加、以後アニメやCMの音楽制作やセッション活動を中心に活動していた上野洋子が、デビュー20周年にして初めて行なったソロ名義ライブを収録したライブアルバム。Zabadak時代の曲からアニメや映画のサントラ用の曲、それにアスタリスク名義による最新作まで幅広い選曲で、それを仙波清彦、鬼怒無月、武川雅寛といった超一流のミュージシャンをバックに演奏。ライブアルバムとは思えない完成度の高い世界を聴かせてくれる。特に中盤の15分近くに及ぶメドレーから、アコースティックギターをバックにした切ないバラード「パラフィン」、そして仙波清彦のドラムが圧倒的な「カモメの断崖、黒いリムジン」への流れは素晴らしい。ムーンライダースの武川雅寛は、ここではヴァイオリン、トランペット、マンドリン、コーラスと多数の楽器を演奏。テクニックを見せるというよりその場その場で曲にあわせた堅実なバッキングに徹していて、彼自身の見せ場とうのはないのが残念だが、それが結果としてライブの完成度に寄与している。DVDも出ているが選曲が違うので注意。

Honzi/one(1996年)
フィッシュマンズのサポートメンバーとしてキーボード兼バイオリンを担当したhonziのソロアルバム。フィッシュマンズではキーボードを主に担当していたわけだが、このアルバムでの音楽性はキーボードと打ち込みのリズムにつぶやくようなボーカルが乗る内省的なもの。無人のメリーゴーランドなどが思い浮かぶようなどこか幻想的でさびしい音楽である。バイオリンはクラシックベースのエレクトリックバイオリンで、決して派手ではないが楽曲にヨーロッパ的哀感を付加している。ヴァイオリンによるインストも2曲ほど演奏されている。
ZYPRRESSEN/ZYPRRESSEN(1996年)
東京で活動する彼らは、ヴァイオリン2名(1人はキーボードも兼)、ピアノ、ベース、パーカッションからなる異色のバンドだ。室内楽的編成によって演奏されるその音楽は、メロディーよりも現代音楽的和声に基づくアンサンブルで静謐でありながら時にドラマチック。その間を重視したような独特な楽曲、クラッシック出身ならではの独特のパーカッションが、このバンドのカラーを作っている。叙情的な楽曲も聴かれる一方、チェンバーロックに通じる実験的でダークな楽曲もある。舞踏集団の音楽を担当していたようだが、それも十分納得できるが全体的な印象としては意外に聞き易い。こういった音楽に対する需要はもっとあるような気がするのだが。ちなみにバンド名はドイツ語の「糸杉」。
坂本龍一/1996(1996年)
ヴァイオリンニストのアルバムではないが、ヴァイオリン入りの素敵なアルバムということでこの1枚。坂本龍一が自分の代表曲を、ピアノ、ヴァイオリン、チェロという編成でセルフカバーし大ヒットとなったアルバム。こういったロマンチックで静謐なセミクラッシック的音楽に対する需要は日本では相当あるはずなのだが、妙に甘ったるいイージーリスニングばかり氾濫して、なかなかそういった坪にはまる作品がない。そんな中でさすが、かゆい所に手が届く見事な作品となっている。坂本龍一ならではの微妙な和音の重ね方は癖になります。個人的には1曲目から6曲目の流れ、特に1曲目から2曲目の並びが気に入っている。後半の曲調に変化が少なく、ちょっとだれる感じがするのがわずかに残念ではある。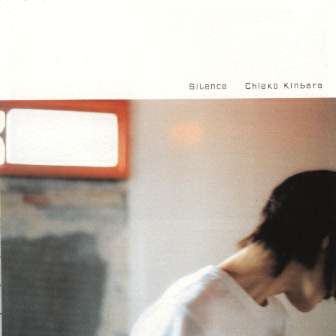
金原千恵子/Silence(2001年)
Brew BrewやAska Stringsに参加。最近は自らのStringsで活動する女性のファーストソロアルバム。その音は打ち込みのリズムトラック、 きらびやかな電子音の上で緩やかにバイオリンの音が響くアンビエントなもの。楽曲自体はメロディアスなものが並ぶのでテクノということではなく、 全体的には極めて淡々と進行する。いわゆるテクニカルなヴァイオリンプレイを期待するとすかされるがその淡く幻想的な楽曲たち、 音世界はなかなか魅力的だ。楽曲はJohn Lennonの「Love」のカバー以外はほぼ彼女自身のオリジナルだ。 ちなみにヴァイオリンの音は完全にクラシックベースの角のないもの。アドリブもおそらくしていないと思われる。
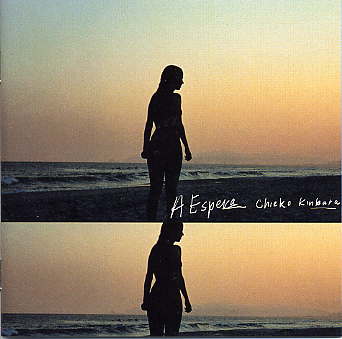
金原千恵子/A ESPERA(2001年)
ストリングスなどを率いて活動するヴァイオリンニストのセカンドソロ。基本的に前作を踏襲した アンビエントな打ち込みサウンドで前作にラテンフレーバーを加えた気持ちよいサウンドが聞ける。 前作でもヴァイオリンはメインではなかったが、今回は前作以上に存在感が薄い。メインメロディを 他の楽器にまかせてバッキングに徹している曲が多く、曲によってはほとんど音が聞こえないものもあるが、 唯一ラストのBrazilでざらついたヴァイオリンプレイを聞くことができる。その代わりと言っては 何だが、今回はボーカルも何曲かで披露している。ヴァイオリンのアルバムとして聴くと、ヴァイオリンの 存在感の薄さにがっかりするが、ラテンの香り漂うアンビエントミュージックとして聴けばなかなかの良作だと思う。

金原千恵子/Paradise(2004年)
1年ぶりの新作は、今までのアルバムとは異なり全編ヴァイオリン弾きまくりの熱いアルバム。 その音は、前作のラテン色を押し進めたクラブサウンド。前作までのどちらかというと内向的な 雰囲気の音から一転した開放的な明るいサウンド、ソロを弾きまくるヴァイオリンが心地よい。 ヴァイオリンの音色はクラシカルなもの。テレビで若い女性タレントがお奨めのアルバムとして 紹介していたがそれも頷ける。ゆったりとしたボサノバなども取り上げてるが、やはり聴き所は クラブ系のアップテンポナンバー。これは久しぶりに一般的にお奨めできる快作。唯一最大の難点はCCCDなのでうちのおんぼろプレイヤーでは聴けないことぐらいか。

BREW BREW/シアワセポップ(1993年)
このバンド、弦楽奏者たちによるポップバンドというコンセプトなのだが、これはなかなか曲者。いわゆるストリングスのアルバムというのは、弦による流麗な音、そして反復リズムが、複雑に入り交じり目眩がするようなアンサンブルを展開、それが音楽的魅力になるのだが、このアルバムも音的にはそういったストリングスものと同じ。そんな複雑なインストルメンタルの上に癖のある男性ボーカルとちょっと甘い女性ボーカルが乗る。ダンスパフォーマンス用に作られた曲もあり、それらの楽曲は結構実験的な際どいところをいっている。曲によってはポップだったりもするのだが、全体的には一般受けする音楽ではない。個人的には気にいってるのだが。

Zabadak/LIVE(1991年)
アイリッシュをはじめとする民族音楽の要素を導入した日本では数少ないポップスDuoのライブアルバム。ギターとボーカルを担当する吉良知彦とアコーディオン、リコーダー、キーボードとボーカルを担当する上野洋子によるその音楽は、どこか懐かしく美しいメロディと高度な音楽性、アコースティックな牧歌的な雰囲気により一部に人気を博した。これはそんな彼らの中期の演奏。ライブではサポートとして、key,b,dr,choそしてヴァイオリンが参加。アイリッシュなどの要素の強いヨーロッパ的香りのするインスト部分において、バイオリンが果たす役割は大きい。5曲目「水の踊り」中間部でのワルツにおけるバイオリンソロは涙ものである。このZabadak現在は上野洋子の脱退で民族音楽色は薄れよりポップな音楽を演奏している。

岡野弘幹と天空オーケストラ/Rainbow Tribe Tour1998(2000年)
関西を中心に活動する7人編成のニューエイジミュージックバンドのライブアルバム。フィドルやブズーキー、アコースティックギターなどアコースティック楽器を多用。インドやチベットなどの民族音楽のエッセンスと、お祭りのかけ声などにも近い力強い歌により独特の世界を作り出している。予想していたイメージとは違い意外とロック色が強い。この躍動感のあるトリップ感覚すら感じさせる音はプログレッシブロックファンに受けそうだ。フィドルは無国籍な民族音楽的な色づけをもたらしている。麻の袋によるジャケットもなかなか面白い。

メトロファルス/俺さままつり(1998年)
ヴォーカルの伊藤ヨタロウを中心とする異色の昭和歌謡ポップバンド(?)、横川タダヒコのバイオリンやライオンメリーのアコーディオン等の楽器から想像されるように彼らは一昔前の「楽団」といったノリで、時に猥雑で時に懐かしくなるような情緒あふれる音楽を展開する。ボーカルの癖の強さがこのバンドの好き嫌いを左右するだろうが、はまると癖になる音楽ではある。横川タダヒコのバイオリンは、トラッドやカントリーの要素もかいま見られ、時にブルーグラス調に、時にヨーロッパ風ジプシー風にといった趣で全編大活躍。このバンドに無くてはならない味付けとなっている。ちなみに残念ながら横川氏は現在、メトロファルスを脱退している。
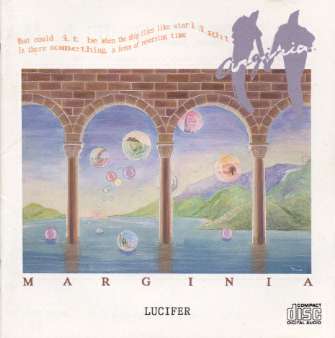
LUCIFER/MARGINIA(1993年)
詳細は不明だが、社会人数人による趣味の作曲プロジェクトによる自主制作アルバムをベルアンティークレーベルがディストリビュートしたもののようだ。バイオリンやマンドリン奏者がおり、ロックフォーマットでありながらアコースティック色が強く、また女性ボーカルの甘い歌声もあり、いわゆるいやし系といった音づくりになっている。なかなか楽曲は多彩でドラマチックな良質なもので、音楽性の確かさ、幅の広さを感じさせる。ただし自主制作のため音質、ミックスに甘さがあり、アルバムトータルとしての完成度を下げてしまっている。女性ボーカルも楽曲によっては違和感が残る。プロデュース次第でかなり善いものになるような気がするのが残念。

TENGO/情熱(2002年)
ジャケットではいまいちピンとこないが内ジャケ見てびっくりのおばちゃん二人組ユニットのセカンド。しかしアコーディオンと ヴァイオリンという最小限の編成によって導き出される熱いプレイはすさまじい。ここで聞かれるアコーディオンは、小林靖宏のような 華やかなイメージではなく、場末感、チープさが漂っていて、それがまたこのユニットの町の音楽士というイメージにぴったりくる。 剣の舞い、リベルタンゴ、チゴイネルワイゼンといった定番の選曲もいやみではなく逆に彼女たちの味になっているところが見事。 個人的にはなじみのメロディが次々と現れるTENGO流スクリーンミュージックメドレーが気に入りました。