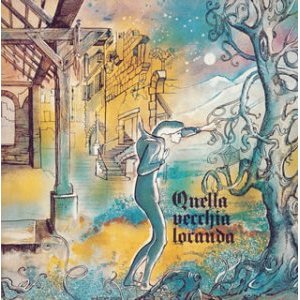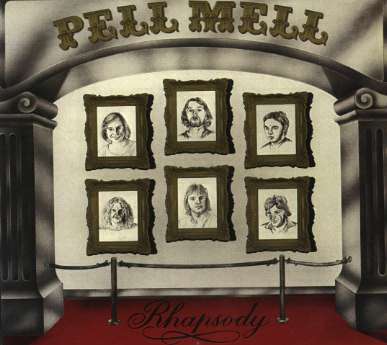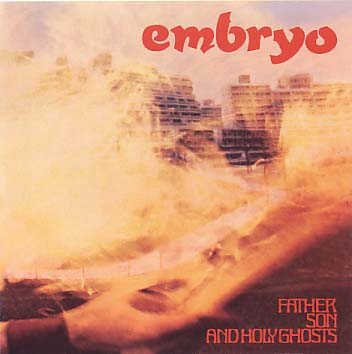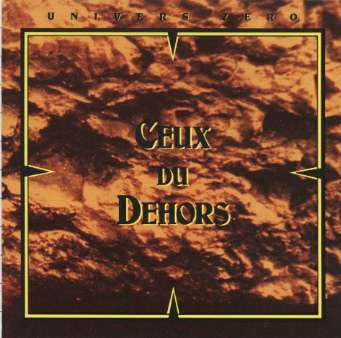�v���Ԃ��6���̃A���o����lj����܂����i2016.2.3�j
|
|
Arti e Mestieri�^Tilt�i�P�X�V�S�N�j ���l�I�Ȏ萔�̃h���~���O�Œm����t���I�L���R������C�^���A�̃W���Y���b�N�o���hArt e Mestieri��1st�B�����o�[�̓L���R�̃h�����𒆐S��b�Ag�AKey�Aviolin�ASax��Vibraphon��6�l�Ґ��B�Ƃɂ����I�n���킵�Ȃ��o�^�o�^�o�^�o�^�Ə�݂�����L���R�̃h�����Ɉ��������邩�̂悤�ɂ��ׂĂ̊y�킪���j�]���Ń����f�B��t�Ő���オ���Ă����悤�ȉ��y���B���̈���Ń����g���������p����Ă�����A�ӂƝR��I�ȃ{�[�J��������p�[�g�Ȃǂɂ͖���King Crimson���v�킹��悤�ȂƂ��������B���Y���I�ɂ̓W���Y���b�N�Ȃ̂����A�W���Y���b�N�Ƃ����ɂ͖��Ƀ����f�B�A�X�������肷�邠���肪�ނ�̌����B���@�C�I�����͂���ȕҐ��̒��ł����܂Ń��j�]���ɎQ������㕨�̈�Ƃ����Ƃ���ŁA�����܂ōۗ�������������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�ނ�̉��y�����Ɠ��̏_�炩����ۂ̓��@�C�I�����̎Q���ɂ��Ƃ��������Ǝv����B |
|
|
Arti e Mestieri�^Giro Di Valzer Per Domani�i�P�X�V�T�N�j ��C�̃{�[�J���X�g���V���ɉ������Ă�2nd�A���o���B�ƌ����Ȃ���{�[�J����������������Ƃ����ĉ̂̕�����������킯�ł͂Ȃ��A�t�ɒZ���C���X�g�Ȃ��R���R���ƃ��h���[�Ŏ��X�ƌJ��o�����\���ɂȂ����B���y�����̂��̂͑��ς�炸�L���R�̒���萔�̃h�����Ɉ��������ăo���h��ۂŎ������銴�������A�����ăV���A�X�ɂȂ肷���Ȃ��g���������f�B�ƋȓW�J�͔ނ�Ȃ�ł́B�O��ł̓����g�����̎g�p���ڗ������̂ɑ��{��ł͂قƂ�Ǖ����ꂸ�A����ɂ��킹�đO��ɂ������R��I�ȃ{�[�J���p�[�g���Ȃ��Ȃ�A���W���Y���b�N�F�������Ȃ��������肪��قȂ�_���B���@�C�I�����ƃT�b�N�X�̃��j�]�����A�_�炩�����������y�ɕt�^���Ă��邠����͑��ς�炸�ŁA���@�C�I�����P�̂Ƃ��Ėڗ��Ƃ���͏��Ȃ��̂����A�ł̓��@�C�I���������Ȃ��Ƃǂ����Ƃ����ƁA���̓Ɠ��̏_�炩�݂������Ƃ����_�ł͕�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���ہA�����o�[���傫���ς�胔�@�C�I�����̎Q�����Ȃ��Ȃ���3rd����͑傫���앗���ς���Ă����B |
|
|
Arti & Mestieri�^Murales�i�Q�O�O�O�N�j 20�N�߂��Ԃ�ɍČ������ꂽArti�̕��A��1��B�����o�[�̓��@�C�I�����ƃT�b�N�X�������A4�l�̃I���W�i�������o�[�ɁA�T�b�N�X�̑ւ��ɂ���1�l�̃L�[�{�[�h�t�ҁA�����ăQ�X�g�̃��@�C�I������Corrado Trabuio�Ƃ����Ґ��B�I���W�i�������o�[�𒆐S�Ƃ����ĕ҂Ƃ������ƂőS�����̒���C�^���A���W���Y���b�N�����҂��Ē����Ɛ���������Ǝc�O�ȏo���B���y���Ƃ��Ă�80�N��̃t���[�W�����ɋ߂��A�t���I�L���R�̎Q���������ő�l�����o�b�L���O�ɓO���Ă��Ă��̋S�萔�̃h�����͂قƂ�ǂȂ��B�悭���������b�N�X�������t�Ƃ������ƂɂȂ邪�A�N���b�N���ɍ��킹�ăX�^�W�I�ŏd�˂܂����ƌ�������̕��ōV�g���̂Ȃ����t�Ƃ��������B�܂��L�[�{�[�h�̃`�[�v�ȉ��F�₢�܂���̃I�[�P�X�g���q�b�g�̎g�p�ȂǁA�f���e�[�v���Ǝv���Ă��܂��Ƃ�����B�y�Ȏ��̂͂���Ȃ�Ɉ����Ȃ����A�Q�X�g���@�C�I�����͂���Ȃ�ɍD�����Ă���̂����E�E�E�B�Ƃ������Ƃł��܂肨���߂ł��܂���B |
|
|
Arti & Mestieri�^ESTRAZIONI�i�Q�O�O�T�N�j �Q�O�O�O�N�ɍČ�������Arti����胁���o�[�̑�ʉ����Ŏ�Ԃ�A���\�����̂��{��B70�N��ɍ�Ȃ��ꂽ�f�ނ��x�[�X�ɑO��≝�N�̋Ȃ̍Ę^�Ȃǂō\������Ă���̂����A�ꌾ�ł����ƌ���B�O�삪�����Ɍ�����c�O�ȏo���������̂ɑ��A�{��̓o���h��ۂƂȂ����G�l���M�[���ӂ�鉉�t���S�҂œW�J����Ă���B�t���I�L���R�̒���h���������N�ɏ���Ƃ����Ȃ������Ȃ��́B�y�Ȃ�70�N��ɔ�ׂĂ����炩�ŗ͋����n���C�F����������ۂŁA�g���������Ղ�����A��ԈႦ��Ƃ������Ȃ邩������Ȃ��y�Ȃ��L���R�̃h�����̃X�s�[�h���Ƃ������̗ʂň������߂Ă���B���@�C�I�����ɂ͑O��ɂ��Q�X�g�Q�����Ă���Corrado Trabuio�������Q���B���[�h�����y�킪�M�^�[�A�T�b�N�X�A�L�[�{�[�h�A���@�C�I�����Ƒ����A�ȓW�J�I�ɂ����j�]�����������ߖ{��ɂ����Ă����@�C�I�����͂���قǖڗ����Ȃ����A�\��������ʂ����ӏ�������ꏖ��I�ȑ��ʂ��ɂȂ��Ă����͂茇�����Ȃ����݂ɂȂ��Ă���B |
|
|
Quella Vecchia Locanda�^Quella Vecchia Locanda�i�P�X�V�Q�N�j �Q���̃A���o�����c���V�O�N��C�^���A�̃v���O���b�V�u���b�N�o���h�̂Pst�B�����o�[��vo���t���[�g�Akey�Ab�Adr�Ag�Ƀ��@�C�I�����̂U�l�Ґ��ŁA�C�^���A�Ȃ�ł͂̃J�E���^�g�D�[�����ۂ��̂��܂킵�A�����y�n�N���V�b�N�̖��t�����Ȃ��ꂽ�A�܂��ɂ��̎���̃v���O���b�V�u���b�N�Ƃ�����ۂ̉��y���B�����t���[�g��Jethro tull�n�̑�����Ԃ悤�ȍr�X�����X�^�C���ŁA���Y�������ƃo�^�o�^���Ă��ă��b�N���������A����قǃ����f�B�ɂ��Ă�������Ȃ��̂ŁA�����܂ŃN���V�J�����b�N�Ƃ�����ۂ͂Ȃ��B���@�C�I�����̓G���N�g���b�N�A�A�R�[�X�e�B�b�N�Ƃ��g���Ă��邪�A�^���̂����������Ă��p�������Ă��ăq�X�e���J���Ȉ�ۂ������B��������Ă��Ȃ��������܂߂��낢��ȈӖ��ŃC�^���A���v���O���炵����i�B |
|
|
Quella Vecchia Locanda�^Il Tempo Della Gioia�i�P�X�V�S�N�j ���@�C�I�����ƃx�[�X�������o�[��サ��2�N�Ԃ�ɔ��\���ꂽ2nd�B�^����ԂȂǂ������đS�̓I�ɑO��ɔ�ׂĐ������ꂽ��ہB�O��̑������t���[�g�͗}���ڂɂȂ�A�S�̂Ƀo���b�N�I�����y�������܂�����������m�ɂȂ��Ă���B�y�Ȃ�����I�Ń����f�B�A�X�ȋȂ������Ă���A���̂���������ꊴ��ł���B�㔼�A�C���X�g���S�Ƀ������R���b�N�ɐ���オ��W�J���݂��镔�������邪���̕����ł��O���̘H���̉������Ƃ��������őS�̂Ƃ��Ă̈�a���͂Ȃ��B���@�C�I�������O��ɂ������q�X�e���b�N���͉e����ߑS�̂ɃX�g�����O�X�I�Ȏg�p�̂�����������Ȃ���Ă���B�Ƃ������ƂőO��ɔ�ׂ�������Ƃ������ꊴ�����芮���x�̍����A���o�������A�l�I�ɂ͑O��̎G���Ȋ������D���������̂ł��̂�����͏��X�c�O�ł͂���B |
|
|
AMON DUUL�U�^TANZ DER LEMMINGE�i�P�X�V�P�N�j �h�C�c�̃T�C�P�f���b�N���b�N�o���hAmon Duul�U�ɂ��Q���g��3rd�A���o���B�q�b�s�[�R�~���[������o�ꂵ���ނ�̓T�C�P�f���b�N�A�W���Y�A�������y�Ȃǂ�Ǝ��ɗZ������70�N��O���Ȃ�ł͂̍��ׂƂ����T�E���h��z���グ���B���̃A���o���ł��\�z���ꂽ�O���ƃW�����Z�b�V�������̌�҂���Ȃ��Ă���B�����ăe�N�j�b�N������킯�ł͂Ȃ��A���y�I�ɐ������ꂽ���̂ł��Ȃ����A���̓Ɠ��̕Ȃ̂��鐢�E�͂Ȃ��Ȃ����[���B�����o�[�̈�lChris Karrer�̓M�^�[�ƂƂ��Ƀ��@�C�I�������S���B�����ď�肢�킯�ł͂Ȃ����̉��F���T�C�P�f���b�N�F�����Ă���B |
|
|
PELL MELL�^Rhapsody�i�P�X�V�T�N�j �h�C�c�̃v���O���b�V�u���b�N�o���h��3rd�A���o���B���̃o���h�̓��@�C�I�������L�[�{�[�h���M�^�[�Ƃ���Thomas Schmitt�Ƃ����l�������[�_�[��vo�Akey�Q�l�Ƀ��Y�����̂U�l�Ґ��B�N���V�b�N�����b�N�A�����W���ĉ��t���邢����V���t�H�j�b�N���b�N�Ƃ������y���ŁA���̃A���o���ł̓��X�g�̊y�Ȃ����`�[�t�ɑs��ȑg�Ȃ��J��L���Ă���B�����A�h�^�o�^�������Y�����A�Â������L�[�{�[�h�̉��F�A�����������������������A�����W�Ɛ����ȂƂ��덡��x�͂��Ȃ荂���B���@�C�I�����̓N���V�b�N���̂܂܂̑t�@�����A�A�h���u�͈�Ȃ��A�܂��^����Ԃ�����Ń��@�C�I�����̉��F���������A�܂��y�Ȃ̒��ŕ����オ���Ă��܂��Ă���B�A�R�M���o�b�N�ɂ�������I�ȃ{�[�J���i���o�[�Ȃǂ͈����Ȃ��̂����B |
|
|
Embryo�^FATHER SON AND HOLLY GHOSTS�i�P�X�V�Q�N�j �h�C�c�̃T�C�P�f���b�N�W���Y���b�N�o���hEMBRYO�B���߂Ē����Ă݂����A���̃A���o���Œ������ނ�̉��y���͂����ɂ����������������A�C���h���y�Ȃǖ������y�̗v�f�̐F�Z���W�����Z�b�V�����F�������̂��B�����o�[�͌�Amon Dull�U�̃h�����A�p�[�J�b�V�������{�[�J��Christian Burchard�����[�_�[�ɑ����̃~���[�W�V�������o����B���̒��ł�����l�̒��S�����o�[�Ƃ��čs�����Ƃ��ɂ����̂�SAX��VIOLIN�Ƃ��ĎQ����Edgar Hofmann�BSax�Ƃ̌����Ƃ������ƂŌ����ăe�N�j�b�N�̃v���C�ł͂Ȃ����A���̉��y���ɂ������T�C�P�ȃ��@�C�I���������X��������Ė��������Ă���B���͎�������������邪���t�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂��B |
|
|
Charles Kaczynski�^Lumiere De La Nuit�i�P�X�V�X�N�j �J�i�_�̃A�o���M�����h���y�W�cConventum�ɎQ�����Ă������@�C�I���j�X�g�̗B��̃\���A���o���B���@�C�I�����𒆐S�ɃM�^�[��s�A�m�ȂǂقƂ�ǂ̊y��𑽏d�^���������̂ŁA�����f�B�I�ɂ̓g���b�h������������A����߂ăN���V�b�N�F�̋����V���t�H�j�[�I�ȍ�i�ɂȂ��Ă���B�y��͂��ׂăA�R�[�X�e�B�b�N�ŁA��{�h�������X�Ńp�[�J�b�V�����������I�ɓ��邭�炢�B�j���R�[���X�̎Q�����@���I�ȕ��͋C��グ��̂Ɍ��ʂ������Ă���B�Ƃ������ƂŖ{��̓v���O���V�b�u���b�N�̔��e�Ō�����i�ł͂���̂������b�N�I�Ȗ������͊F���Ȃ̂ł��̂�����͒��ӁB���@�C�I�����͓��R�̂��Ƃ��N���V�J���ȉ��F�ŃA���T���u���̒��j�Ƃ��Ċ���B�����f�B�A�X�Ō��z�I�ȉ��t���J��L���Ă���B�C�[�W�[���X�j���O�ɋ߂��N���V�J���ȉ��y���������ɂ����߁B |
|
|
UNIVERS ZERO�^CEUX DU DEHORS�i�M��F�j�Ղ̎� �P�X�W�P�N�j 70�N�㖖����80�N�㒆�ՂɊ��������x���M�[�̑O�q���b�N�o���h�̌���3rd�A���o���Bbasoon�Aviolin�Aorgan/piano�Ab�Adr�Ƃ����Ґ��ŁA�`�F���o�[���b�N�Ƒ��ɌĂ��ނ�̉��y�́A�ߌ���N���V�b�N�����b�N�̃��Y�����ɍڂ��ĉ��t�����悤�Ȉ�ۂ��B���̊y�Ȃ̓����f�B�����a���ƃA���T���u�����d���������́B���G�ȕϔ��q�ɂ���Ԃ��ɂ���ăX�s�[�h���𑝂��ēƓ��̂����݂������Ĕ����Ă���B���C���͊NJy��t�҂ƃL�[�{�[�h������Ă��邽�߃��@�C�I�����͘e���ɉ���Ă��邪�A���̃N���V�J���œƓ��ȐF�����́A���̐��ׂ̍��o�C�I�����̐F�Â��ɂ��Ƃ��낪�傫���B����ł͔ނ����������߁A���d���Ȋ����ɉ��F���ω������B |
|
|
Univers Zero�^LIVE�i�Q�O�O�U�N�j 70�N��㔼�`80�N��O���Ƀ`�F���o�[���b�N�̗E�Ƃ��Ċ���A�ꎞ���U �����90�N��㔼�ɍČ������A�ߔN�ł͐ϋɓI�Ƀ��C�u�������s���Ă���x���M�[��Univers Zero�̏��߂Ẵ��C�u�A���o���B ���[�_�[Daniel Denis�̃h�����𒆐S�ɃI�[�{�G�A�R���l�b�g�A���@�C�I�����A�x�[�X�A�L�[�{�[�h�Ƃ����Ґ��Ŏ����̃S�V�b�N �T�E���h��W�J����B�I�Ȃ͍Č�����̃A���o������ŃA���o�����l�̋����I�Ȑ�ւ����Ŕ���A�b�v�e���|�i���o�[�ƃX���[�e���|�� �A�T�ȃS�V�b�N�i���o�[�����邪�A�A�b�v�e���|�i���o�[���~�f�B�A���`�X���[�ȃS�V�b�N�i���o�[���I�Ȃ̒��S�B���̂��� ���b�N�I�ȃ_�C�i�~�Y�������߂�����ɂ͎�ア���������邪�A1�ȖځuXenantaya�v�͂���Ȍ����ɂ��\�������ł�����������ӂ�� ���t�B�e�N�j�b�N�I�ɂ͊����ŃX�^�W�I�A���o�����ƌ��܂������R�Ƃ������t�ł��X�^�W�I�ȏ�̃m���͌����B�t�@���Ȃ�ܘ_�����B |
|
|
DIE KNODEL�^DIE NOODLE!�i�P�X�X�T�N�j ���̃I�[�X�g���A��Die Knodel�́A�ꕗ�ς�������y�����t����o���h���B�����o�[�̓t�@�S�b�g�A���@�C�I����2�l�A�N�����l�b�g�A�g�����y�b�g�A�n�[�v�A�x�[�X�A�M�^�[��8�l��Organisation�ƃN���W�b�g�����l������l�B���̎����y�I�Ґ��ɂ��A�t�H�[�N��|���J�A�����y�A���b�N�A�|�b�v�X�ȂǗl�X�ȉ��y���x�[�X�ɕs�v�c�ȃA���T���u����W�J����B���㉹�y�I�v�f���������A���Ȃ���܂������y�����ӊO�ɂ����̈�ۂ͈��炵�������₷���B�Ȃɂ���Ă͏����{�[�J���̋Ȃ����邪����܂��s�v�c�ȕ��͋C���Y���B�W���P�b�g���R�~�J���ʼn��炵���B�O�q�͋��Ƃ����l�����Ј꒮���B |
|
|
DEVIL DOLL�^Eliogabalus�i�P�X�X�O�N�j �X�����F�j�A�̃v���O���b�V�u���b�N�o���h�̃Z�J���h�B���[��A����͉��ƕ]������悢���BB���z���[�̂悤�Ȓ�����ɁA��ʼn��i�ȃ{�[�J���B�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̃N���V�J���ȃo�b�L���O~�I�[�P�X�g���[�V�����A�C�����M�^�[�A�h����������n�[�h���b�N���ۂ��Ȃ��Ă����肷�邪�M�^�[�\���Ƃ��͂Ȃ��A�����܂Ń{�[�J�����C���B����Ȋ�����1��20���őS2�ȁB����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������̂��낤���A�Ȃɂ��S�̓I��B���L���A�������ǂ����킴�Ƒ_���Ă���߂�����B�o���h�Ȃ̂��v���W�F�N�g���Ȃ̂��A�����o�[���l����̂��A�m��Ȃ��Ă����܂���B���@�C�I�����̓o��V�[���͂��������������A�����܂ŃN���V�J���Ȗ��t���ɏI�n�B�܂������̂���l�͒����Ă݂Ă��������B |
|
|
DEUS EX MACINA�^DE REPUBLICA�i�P�X�X�S�N�j �C�^���A�Ŋ��錻���̃v���O���b�V�u���b�N�o���h��3rd�B�W���Y���b�N�̃X�s�[�h���ƕϔ��q�̐�Ԃ��A�n���C���y�̉e���������G�L�Z���g���b�N�ŕΎ��I�ȃ{�[�J���A�M�^�[�̃n�[�h���b�N�I�Ȏ����A�����ăo�C�I�����̕s�����������o���G�L�]�`�b�N�ȉ��F�B���Ƃ��Z���C���[�W�������o���o���h�ł���B�Ƃ����킯�ŁA�Ȃ��Ȃ���ʎ���Ƃ͎v���Ȃ��̂������̃I���W�i���e�B�Ɗy�ȁA���t�̂����͈꒮�ɏ\���l������̂��B�o�C�I�����͎��Ƀq�X�e���b�N�Ɏ��ɏ�M�I�ɋߌ���I�ȃX�P�[���ɂ̂��ēƓ��̃\�����J��L���A���̃o���h�ɖ����Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ɂȂ��Ă���B |
|
|
Mago de Oz�^LA LEYENDA DE LA MANCHA�i�P�X�X�V�N�j �ڍׂ͔���Ȃ����X�y�C���̃��@�C�I��������w�r�[���^���o���h�ɂ��h���L�z�[�e���e�[�}�ɂ����R���Z�v�g�A���o���B������w�r���^�����̊y�Ȃ̒��ɉ��̂����@�C�I�������\��������Ă���s�v�c�ȃo���h���B���Ƃ��Q�Ȗڂł͓T�^�I�ȃw�r���^�̊y�Ȃ��炢���Ȃ�ԑt�ɓ���ƃ��@�C�I�������n���K���[���Ȃ�e���o���B�����{���́u�n���K���[���ȁv���d���𑽗p�����y�Ȃł���̂ɁA�����ł̉��t�͒P�������ł��邠����A�e�N�j�b�N�I�ɂ͋^��̗]�n������B�܂����F�̓}�C�N�ŏE���Ă͂���̂��낤�����S�ɐ����ň�؉��H����Ă��Ȃ�������������[���B���̂����Ȃ����S�Ƀg���b�h�̊y�Ȃ������Ă���A�ӊO�Ƃ����炪���̃��@�C�I�����j�X�g�̖{�E�Ȃ̂ł͂Ƃ����C������B |
|
|
Midian�^SOULINSIDE�i�P�X�X�S�N�j �C�^���A�̃v���O���b�V�u�w�r�[���^���ƌ����ׂ����قȉ��y���̃o���h������Midian���B�M�^�[��{�[�J���Ȃlj��y���̃x�[�X�͊��S�Ƀw�r�[���^���Ȃ̂����A�A���o���`�����瑽�p�����ϔ��q�̐�ւ����ƁA���G�ɍ\�z���ꂽ�y�ȁB�����ėv���v���ŏ���I�ȃ��@�C�I�������o�ꂵ�A�N���V�J���ȕ��͋C���������o���B���@�C�I�����̓�������AMago de Oz�̂悤�ȋ������͂Ȃ�����߂ăX���[�Y�A�Ƃ��̉��y�͂���߂ēƎ��̃X�^�C������肠���Ă���B���@�C�I���������ɂ��܂�3�Ȗڂ�ac-g�Ƃ̃f���I�Ȃnj����ɕ������Ă����B�����S�̂̈�ۂƂ��āA�y�Ȃɂ��������L���b�`�[������������̂����A�Ƃ��������������B�ϔ��q�����܂�y�ȂɃv���X�ɓ����ĂȂ��悤�ȋC������̂����ǂ����낤�B |
|
|
Grauco Fernandes�^Grauco Fernandes �u���W���̃��@�C�I�����j�X�g�̃\���A���o���B���̐l���̓v���O���b�V�u���b�N�o���h�ɂ��Q�����Ă���悤�����A�����Œ������̂̓G���N�g���b�N�o�C�I�������[���ȉ��F�����郁���f�B�A�X�ȃW���Y���b�N�C���X�g�BG�Akey�Adr�Ab���o�b�N�ɁA���o�[�u�̂����������F�ŏ�L���Ȕ������C���X�g������B�y�Ȃ͂قƂ�ǂ̕�������������ƍ�肱�܂�Ă���悤�ŁA�A�h���u�p�[�g�͏��Ȃ��A�������C���^�[�v���C�Ƃ����������ł͂Ȃ����A�y�Ȃ̂悳�ŋC�����悭������B����3�Ȗڂ́uSoli�v�̓G���N�g���b�N���@�C�I�����̉��F���f���閼�ȁB�͂�����̂Ȃ��L���ȉ��y���͑f���炵���B |
top�ɖ߂�