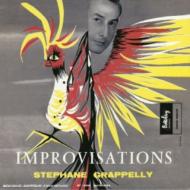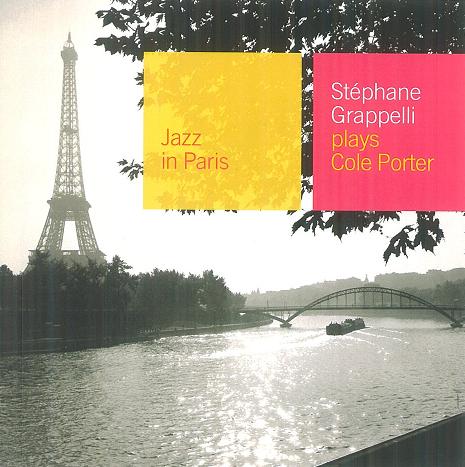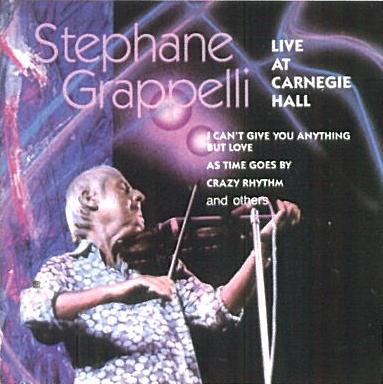Django Rheinhardt and the Quintet of the HOT CLUB OF FRANCE /DJANGOLOGY(1949年)
Stephan GrappelliとDjango Reinhardtは34年にギター3本、ベース、ヴァイオリンという弦楽器だけの編成でフランスホットクラブバンドを結成ともに活動する。第二次大戦によりその活動は中断するが、終戦後の47年に二人は再会、Djangoが53年に亡くなるまで断続的に活動を続けた。このアルバムはそんな彼らの活動再開後のライブ録音。名義としてはthe Quintet of the Hot Club Of Franceだがここでの編成は、Django、Grappelliにベース、ピアノ、ドラムというもの。リズム的にはあくまでスイング時代の2ビートサウンド。Djangoならではの「ジャラララララン」という派手なカッティングと粒立ちのいい気品のあるソロの組み合わせ、一方あくまでもおだやかにやわらかいGrappelliのヴァイオリンという好対照がこの音楽の魅力だろう。会場で素人が録音したものということでノイズが多く、この時代にしても音質はかなり悪いが、演奏そのものはダイレクトに捉えられていて逆に会場録りならではの臨場感があり、そこが魅力だったりもする。
Stephane Grappelli/Improvisations(1956年)
名ピアニストMurice Vanderに、Bud PowellやMiles Davisとの競演歴もあるベーシストPierre Michelot、ドラムBaptiste Riellesというメンバーでのカルテットでの録音。Django Reinhardtが53年に亡くなって数年、ハードバップ全盛の時代、パリでホテル付ミュージシャンとして地道に活動してた時期の録音になるわけだが、数年前までDjangoとやっていたサウンドとは打って変わってハードバップなスタイルのバックにのって、バリバリとソロを弾いていて驚かされる。彼自身のスタイルは昔から晩年までと変わらない歌いまくる流麗なフレージングなわけで、バックのハードバップ的4ビートに対しては若干甘い感じもするが、それでも手癖で一気に駆け抜けてしまう印象のある晩年に比べ、ビートを意識して考えながらソロを作っていっている感じの場面もあり興味深い。選曲は「Fashinating rhythm」「S’wonderful」「Time After Time」など彼らしい古めのスタンダード中心。「Nigthingale Sang In Barkely Square」あたりは珍しい選曲か。モノラル録音。現在「Jazz in Paris」シリーズとして3曲のボーナストラック入りでリイシュー。
Stephane Grappelli/Feeling+Fitness=Jazz(1962年)
66年のViolin Summitで再度脚光を浴びる前の録音が少ない時期のスタジオ作品。メンバーはギターにLeo PetitとスイスのPierre Cavalliの2人、ベースにMartia Solarバンドに在籍していたGuy Pedersen,ドラムには当時若手俊英のDaniel Humairという編成。再発盤ではタイトルが「Django」に改められたことと、ギター入りという編成からDjango Reinhardtを意識しているような印象があるが、その「Django」はJohn LewisがDjango追悼として作った曲。そこで聴かれるGrappelliの攻撃的なフレージングは非常にかっこよく、流麗な中にも確かなグルーブ感が感じられる。ほかの選曲には「Minor Swing」「Nuages」「Daphne」など確かにホットクラブ時代のレパートリーが多いが、それらもスイングスタイルではなくあくまでバップとして再解釈されて演奏されている。この時期の彼の作品は、録音数こそ少ないが1枚1枚しっかりと作られている印象。現在Jazz In Parisシリーズで「Django」のタイトルで再発されていて、そちらでは2曲追加あり。このシリーズのジャケットは正直いただけないのだが廉価版でもあるしそちらがお薦めか。
Stephane Grappelli・Barney Kessel/I Remember Django(1969録音)
Charlie Christian系のジャズギターリストの名手と名高いBarney Kesselとの連名作。編成は2人+リズムギター、ベース、ドラム。「With The New Hot Club Quintet」というクレジットやDjango時代のレパートリーを中心とした選曲、そしてKesselの手によるDjangoへの追悼ナンバーの収録など多分にDjangoとHot Club Quintetを意識した作品。ただそれはあくまで精神的な部分ということで、Kesselのスタイルはあくまで彼ならではのバップよりのモダンなギタースタイルで、その快活でリズミカルな粒立ちのいいギター、プッシュ気味の演奏にあわせてかアップテンポ曲でのGrappelliのヴァイオリンも滑らかないつものスタイルながら丁寧さより歯切れ重視の演奏になっている。アルバム全体としてはオープニングのムーディな標題曲始めスローテンポのゆったりした曲が半数を占めることが落ち着いた印象を与えており、ギター、ヴァイオリンという楽器そのもののたたずまいもあってジェントルな印象が強い。ただアルバム後半に行くにつれアップテンポナンバーでの白熱した掛け合いも。ラストの「It’s Only Paper Moon」などはミドルテンポでパンチの効いたプレイが素晴らしいなかなかの名演になっている。
Barney Kessel・Stephane Grappelli/Limehouse Blues(1969録音)
「I Remember Django」から2年たった71年になって、同一セッションからの新たな8曲をチョイスして発表されたのがこのアルバム。「I Remember Django」が割と繊細な演奏を中心に収録していたのに対し、冒頭の「It Don’t Mean A Thing」を始め アップテンポのナンバーが多く収録され良くも悪くもラフで勢いのある曲が多くセッション的雰囲気が強い。「Tea For Two」などゆったりした曲すら途中からアップテンポになりギターがソロを取り巻くっている。その一方でボサノバタッチのKesselのオリジナル「Little Star」など興味深い選曲もみられる。前作とはクレジットの順番が逆転しBarney Kesselが先になっているように心なしかギターの音量が大きくフューチャー度が高いような気もする。もちろんGrappelliも活躍しているし作品レベルとしてはひけをとらないので、収録曲や曲調の好みで好きな方から聴けばいいと思う。
Gary Burton&Stephane Grappelli/PARIS ENCOUNTER(1969年)
ヴィヴラフォンの名手Gary BurtonとGrappelliという異色の取り合わせによるアルバム。GrappelliがBurtonの腕前に感動し、Burtonのヨーロッパツアーに伴って実現したセッションだったということで、ドラムとベースはBurtonのバンドメンバー。BurtonバンドにGrappelliがゲスト参加したという形。ピアノなどのバッキング楽器がいないため、バイオリンとヴァイブという高音域楽器同士が渡り合う様がストレートに味わえるのはきわめて新鮮。特に、ドラムが派手にシンバルを鳴らしプッシュしまくるプレイスタイルのため、定番の「Daphne」からしていつも以上のハイスピード、Grappelliもそれにあわせてアタックの利いたアグレッシブな演奏を展開。一方Miles作の「Blue In Green」や「夜は千の目を持つ」など普段Grappelliが取り上げないようなジャズスタンダードもとりあげそちらではリリカルで美しい演奏を聞かせてくれる。Grappelliの多彩な競演歴の中でもトップクラスの素晴らしい作品。
Stephane Grappelli/AFTERNOON IN PARIS(1971年)
スイング感あふれるベルギー人ピアニストMarc Hemmeler、後にECM系で活躍するドイツ人ベーシストEberhard Weber、Be-bop期に大活躍した後ヨーロッパに移住した名ドラマーKenny Clarkeというカルテット編成による録音。全体的に軽快でやわらかいタッチで小粋にスイングするジャズという印象。Grappelliのプレイスタイルの特徴は流麗さはポルタメントとビブラートの多様、そしてそのとどまるところなく続くアドリブソロの音選びにあるのだが、ここではBop的にプッシュされることもなく、のびのびと彼の持ち味を存分に出してプレイしている。逆に、Bop的なアタック感などには若干欠けるが、Grappelliの流麗でおしゃれな室内楽的ジャズというスタイルではひとつの完成形ともいえるのではないだろうか。選曲は「Undecided」「Tangerine」「Nuage」などの定番に、「Afternoon In Paris」「枯葉」など。「Afternoon In Paris」のさわやかに歌うソロ、「枯葉」の意外に攻撃的に畳み掛けるプレイなどはこのアルバムの聴き所だろう。
Stephane Grappelli/Parisian Thoroughfare(1973年)
Black Lionレーベルからの本作は、ツアー中のThad Jones Mel Lewis楽団のリズム隊であるRoland Hanna (p) George Mraz (b) Mel Lewis (ds)を迎えての録音。ジャズ王道のメンバーを迎えたことで、Grappelliのこの時期の作品の中でも特にジャズ本道をいくアルバムになった。タイトでプッシュしまくるリズム隊により、えもすると前ノリのスイングになってしまうGrappelliもグルーブ感とつややかさを兼ね備えたソロをとり、それにRoland Hannaの弾く絶妙なピアノがモダンな色を添える。楽曲も「Love For Sale」「Parisian Thoroughfare」「Wave」「Hallelujah」と名曲ぞろい。Hanna作曲の悲しくも美しい「Perugla」やショパンの「プレリュードE短調」をベースにした即興もすばらしい。Grappelliは70年代が全盛期だというのが個人的意見だが、その中でも選曲、メンバー、演奏すべてがそろった群を抜く名盤だと思う。
Stephane Grappelli/Plays Cole Porter(1975年・76年)
「It's All Right With Me」「Love for Sale」「You'd be So Nice To Come home To」など ジャズファンならずとも聴いたことのある名スタンダードを数多く生み出した名作曲家Cole Porter。このアルバムはその彼の作品からの選曲された作品。メンバーはオルガンのEddy Louiss、ドラムのDaniel Humairを中心に曲によってピアノやギターが加わる編成。60年代にJean-Luc Pontyとのトリオでハードバップばりばりの演奏を繰り広げていた2人が中心になっているだけに、Grappelliのアルバムの中でも特にHard Bopよりのモダンで激しいアルバムとなった。冒頭の「It's All Right With Me」からして高速のリズムにのってGrappelliにしてはアタックの利いた太い音で激しいソロをとっていてこれが素晴らしい。他の曲でも流麗ながらエッジの利いた音色でのソロが心地よい。これ以後、Grappelliの音は飄々としたタッチの独特のスタイルへと向かって行くわけで、骨太なタッチで4ビートに向かって行ったGrappelliの最後期の姿を収録した作品となった。Porterの曲の良さもありGrappelliの作品の中でも大好きな一枚。
George Shearing meets Stephane Grappelli /Reunion(1976年)
1939年に戦争でイギリスからフランスに戻れなくなったGrappelli は40年代前半イギリスで活動を継続。その時に知りあった盲目のジャズピアニストGeorge Shearingとギター、ベース、ドラムという編成で終戦まで活動をともにした。その後Grappelliはフランスに帰国、一方のShearingはアメリカに渡りピアニストとしても「バードランドの子守唄」などの作曲者としても名声を博す。そんな2人が30年ぶりに共演したのがこのアルバム。ShearingのトリオにGrappelliが参加した形で、「I'm Coming Virginia」「Time After Time」「Don't Mean A Thing」「Makin' Whoopee」など昔からの定番曲を選曲、Shearingの柔らかく小粋にスイングするピアノにのってGrappelliもしっかりとした音使いながら優美な音色でのびのびとプレイしている。Grappelliが幾度と取り上げている「Don't Mean A Thing」などはイントロのアレンジも粋なこの演奏が個人的にはベストテイク。
Stephane Grappelli/Uptown Dance(1978年)
CBS移籍第1弾にして初のアメリカレコーディング作品。ジャズ系とフュージョン系の2組のセッションミュージシャンチームを用意してのレコーディングというあたりGrappelli、レコード会社とも気合が入っていたと思われる。ジャズ組はRon Carter(b)、 Grady Tate(dr)ら名うてミュージシャン、フュージョン系もRichard Tee(key)、Steve Gadd(dr)といったSTUFFメンバーやAnthony Jackson(b)など豪華。全体のサウンドは分厚いストリングスをバックにしたおしゃれなBGM風で統一されつつ、それぞれの組ごとに持ち味が発揮されている。特にフュージョン組での演奏は、ミディアムテンポでアーバンなもので、まるでNoel Pointerのアルバムを聴いているかのような錯覚を覚える。Grappelliもいつものつややかな音色でありながら、より横ノリ感のあるフュージョン風のタッチでの演奏を試みている場面もあり、これが意外にもはまっている。一方、ジャズ組はさわやかなストリングスをバックにいつもの軽やかな演奏を展開。というわけでBGMとしても聴け、演奏面でも聴ける秀作にしあがっている。
Stephane Grappelli/Live at Carnegie Hall(1978年)
カナダ出身でイギリスで活動していたギターリストDiz Disleyは70年初頭にGrappelliを野外フェスに招聘、彼がフォークやスイングミュージックの文脈で新たな人気を獲得し晩年において世界中で演奏することになるきっかけを作った。そのDizと、Soft Machineなどジャズロックの世界でも活躍していたイギリスの腕利きギターリストJohn Etheridge、それにGeorge Shieringとの共演などで知られるベースのBrian Torffというトリオを従えてGrappelliがニューヨークカーネギーホールで行なったライブ録音。Grappelliは2本のアコースティックギターとベースが繰り出す切れのいいリズムにのって歌うように奔放なソロをとっている。彼は60年代〜70年代にかけてジャズコンボを相手に4ビートジャズと自己のスタイルの統合を模索していたわけだが、ここではその束縛から解放されたかのようにのびのびと演奏している。「Crazy Rythm」「Nuages」など定番中心だが、珍しい選曲としてJean-Luc Pontyの「Golden Green」(「Ponyと佐藤」収録)を取り上げていて、オリジナルとは異なるアコースティックで美しい演奏は素晴らしい。
Stephane Grappelli/Young Django(1979年)
当時30代後半で俊英ギターリストとして活躍していたPhilip CatherineとLarry Coryellの2人、それにデンマークを代表する名ベーシストNiels Henning Orsted Pedersen、そしてGrappelliという4人によるこの録音は、タイトルからもわかるように若い世代のミュージシャンによりDjango ReinhardtとGrappelliのHot Club Quintetの再現を意図したもの。選曲もCatherine、Corryellによるトリビュートナンバー2曲を除き全てGrappelli、Djangoの共作曲。選曲はCatherineが行ったとのことで、Djangoの影響を受けたというCatherineが中心となって行われたセッションのようだ。実際、演奏においてもCatherineはDjnagoを思わせる特徴的なギターのかき鳴らしを聴かせてくれる。もちろん、世代も異なるメンバーでの演奏なのでHot Clubをトリビュートしながらもよりモダンな切れと優雅さのある録音が心地よい。Grappelliはいつもながら優雅に歌いスイングする演奏。収録曲の中では特に「Tears」の演奏が素晴らしい。
Stephane Grappelli・Martial Solal/Happy Reunion(1980年)
フランスを代表する技巧派ピアニストとの完全Duo作品。Solalは、トラディッショナルからモダンまで幅広い技巧を使い分ける名手で、このアルバムでも、そういったさまざまな面を聞かせてくれる。Grappelliの方は70年代後半以後の流れで、グルーブ感よりも、つっこみ気味のタイム感とフレーズのつみこみが、前に出る印象。そのためか全体に突っ走るGrappelliのヴァイオリンにSolalがあわせている印象がある。その一方Grappelliのいつものオーソドックスなフレージングに対し、Solalは調性などにおいてモダンなアプローチでのバッキングが際立っていて、それがこのアルバム独自のカラーになっている。現代音楽っぽい不安感をかもす即興をする「Et si L'on improvisait?」などではGrappelliもSolalに触発されてか珍しくシリアスなアプローチも展開。全体的にヨーロッパのジャズならではの味わいがあり、同じ編成ながらアプローチの異なるMcCoy TynerとのDuoと聞き比べるのも面白いかもしれない。
Stephane Grappelli & Yehudi Menuhin/The Very Best of Grappelli & Menuhin(1973年〜85年)
クラシックヴァイオリンの巨匠MenuhinとGrappelliはBBCのテレビ番組の企画で共演して意気投合、70年代〜80年代に数枚のアルバムを作った。そのベスト盤が本作。選曲は「Night and Day」「Autumn Leaves」「My Funny Valentine」などのメロディアスなスタンダード。一部にストリングス物もあるものの、ほとんどはベース、ドラム入りのジャズフォーマットでの演奏。ただ、当然Menuhinはアドリブが弾けないので、どの曲もスロー、ミディアムテンポできっちりとアレンジされていてイージーリスニング風の仕上がりとなっている。Grappelli自身のプレイスタイルがポルタメントを利かせた柔らかなタッチの優雅なものだけに、Menuhinのクラシックそのもののスタイルとの相性は抜群。Menuhinもアドリブ風の演奏を心がけているので、パッと聴き細かいビート感の違いを意識しなければあまり違いがわからなかったりもする。まあジャズではないわけだが、癒し系イージーリスニング作品としては一級品の出来だろう。
Stephane Grappelli・Toots Thielemans/Bringing it together(1984年録音)
ジャズ界を代表するバイオリンニストとハーモニカ奏者によるコラボレイトアルバム。他のメンバーは当時のGrappelliのツアーメンバーで、80年代に共演を重ねたイギリス人ギターリストMartin Taylor、同じく晩年まで片腕として行動をともにするフランス人の若手ギターリストMarc Fosset、それにベースのBrian Torffという編成。ドラムレスということもありギターを中心としたゆったりとしたアコースティックスイング的なビートにのって、達人2人がゆったりとした柔らかい音色で華麗なソロを取り合う歌心とスイング感あふれるアルバムになった。選曲は「Bye Bye Blackbird」「Georgia On My Mind」「As Time Goes By」などGrappelliの定番曲に一部に「恋人と別れる50の方法」などポップス系のユニークな選曲も見られる。Bop的スリルは一切ないがヴァイオリンとハーモニカによる優美で哀感あふれるアコースティックジャズを聴きたい向きには存分に楽しめるアルバム。
Stephane Grappelli/Plays Jerome Kern(1987年)
アメリカを代表する作曲家Jerome Kernの作品を演奏した作品集。Jerome Kernは「Yesterdays」「All The Things You Are」「Smoke Gets in Your Eyes」といったジャズスタンダードとしても有名な曲の作曲者。というわけで結果としては所謂スタンダード集といってもいい選曲になっている。レコーディングメンバーとしてはMarc Fossett 、Martin Taylorと80年代のGrappelliを支えた2人のギターリストらが参加しているが、アレンジが基本的にストリングスをバックにボサノバタッチのギターなどを配しての演奏で所謂ムーディなBGMといった雰囲気が支配的で、バンドによる攻撃的な演奏を期待すると肩透かしをくらう。何曲かではリズム隊入りの曲もありそれらの曲ではジャジーな演奏を楽しむことができるが、全体としてはイージーリスニング寄りの作風であり80年代以後の浪々と歌い上げるGrappelliのヴァイオリンを楽しむための作品というところ。
Stephane Grappelli・McCoy Tyner/ONE ON ONE(1990年)
GrappelliとジャズピアニストMcCoy Tynerとのデュオアルバム。彼は60年代にJohn Cotraneのバンドに参加、以後もバンドやソロピアノなど様々ななスタイルで活動を続けるモダンジャズの重鎮。ジャズピアニストメインストリームの彼とスイングジャズのGrappelliとの取り合わせは少々異色ながら上々。McCoyのコード弾きを中心としたアグレッシブで華やかなアタックの利いたピアノプレイか繰り出されるビート感に触発されたのか、Grappelliもメロディアスで優美なトーンを維持しつつもいつになくアタックの利いた4ビートを感じさせる芯のあるプレイを展開。曲によってMcCoyのビートに対してGrappelliのプレイにはグルーブ感に関して甘さを感じさせる瞬間もあるが、全体としては充実した内容の好盤となった。選曲は「How High The Moon」や「I Got Rhythm」などの定番曲にMcCoyによる名ブルース曲「Mr PC」など。定番曲と言えどもいつもと違う魅力を放っている。
Stephane Grappelli・Michel Legrand/Legrand Grappelli(1992年)
ジャズピアニストであり映画音楽などの作編曲家としても知られるフランス音楽界の重鎮Michel Legrandとの競演アルバムであるこの作品は、分厚いストリングスやゴージャスなブラスのビッグバンド、時に女性コーラスをも従えての豪華なムード音楽という趣の作品集。Grappelliもいつもの軽快なスイングジャズとは雰囲気を変えムードたっぷりにヴァイオリンを奏でている。一方Legrandのピアノはスイング感をおさえ、美しくヴァイオリンをバックアップしている。選曲は「枯葉」「My Man」などのシャンソンやLegrandの作曲した映画音楽などが中心。またGrappelliが89年に映画「5月のミル」のサントラを担当した際にその1曲として作った「Riviere」やHot Club Band時代からのレパートリー「Nuages」も取り上げられている。どれもストリングスをバックに優雅に美しく演奏されている。というわけで所謂ジャズを期待するとすかされるが、最高級のBGMが楽しめる作品。
Stephane Grappelli/SO EASY TO REMEMBER(1993年)
85歳を記念して録音されたというこのアルバムはギターリストにKenny BurrellとBucky Pizzarelli、ベースにRonCarter、ドラムにGrady Tateなどそうそうたるメンバーが参加。ギターのクリアトーンに若干エコーの利いたサウンド、ブラシ中心で軽快にスイングするドラム、その上で終始優美なトーンで演奏されるGrappelliのヴァイオリンとあって非常に上品な印象を受ける。実際「煙が目にしみる」「In A Sentimental Mood」などのメロディアスではいかにもというスローテンポナンバーが多く、これらの曲ではイメージ通りのムーディな演奏となっているのだが、「Love For Sale」「How High The Moon」あたりの曲では、繊細でありながらアグレッシブでしかもプッシュしまくりのリズム隊にのって、上品でありながら奔放なGrappelliならではのソロが本当に素晴らしい。2人ギターの職人芸的ソロも心地よい。イージーリスニングとして気軽に聴くにも、純然たるジャズとしても真剣に鑑賞するにも耐えるGrappelli晩年の集大成とも言える録音。
Stephan Grappelli・Michel Petruciani/Flamingo(1995年)
97年に亡くなる2年前、Grappelli最晩年の録音で、フランス人ながら若くしてアメリカに渡り活躍し天才の誉れ高かったジャズピアニストPetrucianiと組んでのスイング感あふれる1枚。ドラムにRoy Haynes、ベースにGeorge Mrazというやはり名うての2人を迎えパリで録音された。この時期のGrappelliのヴァイオリンは一音一音にポルタメントを利かせたような、翻るような彼独特のタッチがより激しくなっている傾向にがあるがこのアルバムは特にその印象が強い。「Sweet Georgia Brown」などのアップテンポナンバーでのHaynesらリズム隊の、身軽さを感じさせながらもかなりプッシュを利かせ金物などの鳴りも激しいタイトでパワフルな演奏に対しても、Grappelliはその彼独特のタッチにより、飄々とすりぬけるかのように歌うようなソロをつむいでいる。一方のPetruccianiも軽やかなタッチで歌うようにプレイしGrappelliの相性は抜群、タイトなリズム隊との好対照ぶりもあって一級のアルバムとなっている。スローナンバーでの上品な演奏も素晴らしい。この後2人とも相次いで亡くなってしまったのが本当に残念。